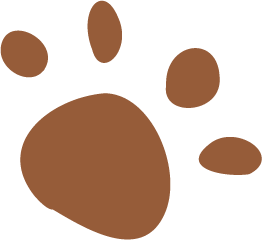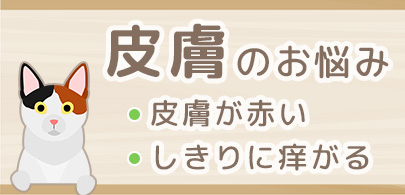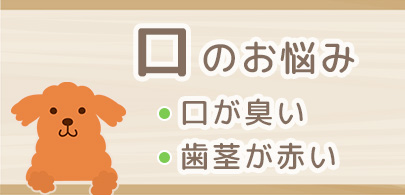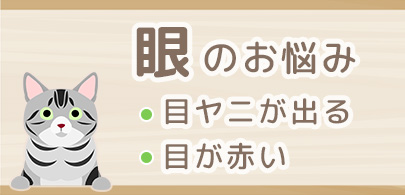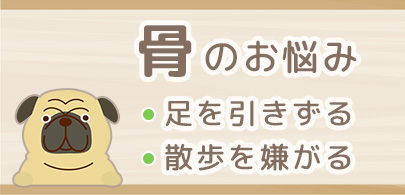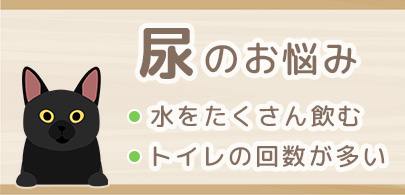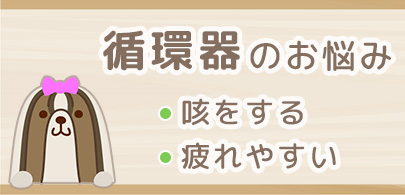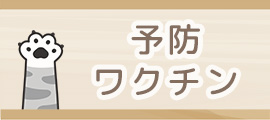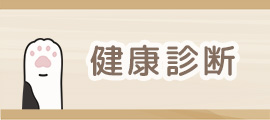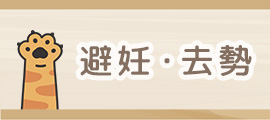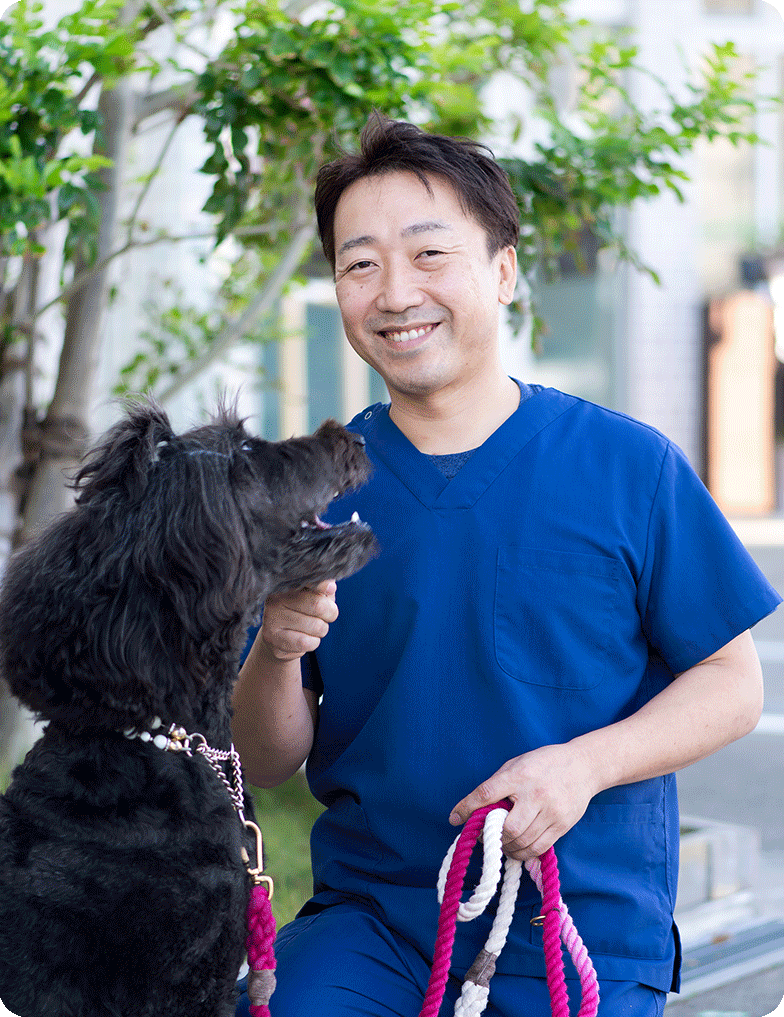浜松市近隣にお住いの飼い主様へ、犬のクッシング症候群を徹底解説!
|はじめに
浜松市近隣にお住いの飼い主様から、愛犬の体調について次のような相談をよくいただきます。
「最近、水を大量に飲むようになった」
「トイレの回数が増えた」
「お腹がぽっこり出てきた」
「毛が薄くなってきた」
これらの症状は「老化現象かな」と見過ごされがちですが、実は クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症) が関わっている可能性があります。本記事では、クッシング症候群の原因・症状・診断・治療・日常管理までを、獣医師の実体験を交えて詳しく解説します🐶
|クッシング症候群とは?
犬 クッシング症候群は、副腎から分泌される「コルチゾール」というホルモンが過剰に分泌されることで起こる病気です。コルチゾールは本来、ストレスに対抗したり炎症を抑えたりする重要なホルモンです。しかし必要以上に分泌されると、代謝の異常、筋肉や皮膚の萎縮、免疫力低下などを引き起こし、生活の質を大きく下げてしまいます。
|コルチゾールの役割と過剰分泌の影響
コルチゾールの役割は以下のようなものがあります。
・炎症を抑える
・血糖値を上げる
・ストレス反応を調整する
・エネルギー代謝を助ける
しかし、過剰分泌が続くと以下のような悪影響が出ます。
・筋肉の萎縮 → 運動能力の低下
・皮膚が薄くなる → 傷の治りが遅くなる
・免疫力低下 → 感染症を起こしやすい
・内臓負担 → 肝臓や腎臓の障害リスク上昇
|クッシング症候群の発症タイプ
クッシング症候群は、大きく3つのタイプに分けられます。
1.下垂体性(約80〜85%)
脳の下垂体にできた腫瘍がACTHというホルモンを過剰に分泌し、副腎を刺激してコルチゾールを出しすぎてしまうタイプです。
2.副腎性
副腎そのものに腫瘍ができ、直接コルチゾールを過剰に分泌します。外科手術での対応が必要になるケースがあります。
3.医原性
長期的にステロイド薬を使用した結果、副作用として発症するタイプです。薬の使用を見直す必要があります。
|クッシング症候群の症状と初期サイン
犬 クッシング症候群は「老化」と見間違われやすい病気です。特に以下のような症状が出た場合は注意が必要です。
多飲多尿
1日に体重1kgあたり100ml以上の水を飲んでいる場合は「多飲」と判断されます。例:5kgの犬が毎日500ml以上の水を飲む。
お腹の膨らみ(ポットベリー)
筋肉が萎縮し、腹部だけが膨れたように見える典型的な症状です。実際にトイ・プードルの飼い主様から「痩せたのにお腹だけ出ている」と相談を受け、検査の結果クッシング症候群と診断した例があります。
皮膚や毛の異常
左右対称の脱毛や皮膚の菲薄化(薄くなる現象)、皮膚感染が起こりやすくなります。
行動の変化
散歩を嫌がる、階段を登れない、寝てばかりいる、などの症状が現れます。
|診断方法と検査
当院(TPC浜松動物総合病院)では、以下の検査を組み合わせて犬 クッシング症候群を診断します。
血液検査
肝酵素のALPが高値を示すことが多く、中には1,000以上、重症例では2,000を超えるケースもあります。
ホルモン負荷試験
- ACTH刺激試験
- 低用量デキサメタゾン抑制試験
これらは副腎が正常に働いているかを確認するための代表的な検査です。
画像診断
腹部エコーで副腎のサイズや腫瘍の有無を調べます。
尿検査
尿中コルチゾールとクレアチニンの比率を測定し、補助診断として活用します。
|クッシング症候群の治療法
治療法はタイプや犬の年齢・体調によって変わります。
下垂体性の治療
最も多いタイプで、トリロスタンという内服薬を使用します。投薬開始後は定期的な血液検査で副作用を確認しながら継続します。
副腎性の治療
副腎腫瘍が原因の場合は外科手術で摘出することがあります。ただし高齢犬や心臓病などを併発している場合はリスクが高いため、慎重な判断が必要です。
医原性の治療
ステロイド薬の投与が原因の場合は、獣医師の指導のもとで減量や中止を行います。
|放置するとどうなる? 併発症に注意
犬 クッシング症候群を放置すると、以下のような合併症を起こす可能性があります。
・糖尿病
・高血圧
・膵炎
・皮膚感染症
・血栓症
これらはいずれも命に関わるリスクがあるため、早期の治療開始が非常に重要です。
|当院での症例紹介
10歳のミニチュアダックスが「水を異常に飲む」と来院しました。血液検査ではALPが2,000以上と高値を示し、ACTH刺激試験で陽性。クッシング症候群と診断しました。内服治療を開始し、1か月後には飲水量が半減し、散歩を楽しめるようになりました。飼い主様から「また若返ったみたい」と喜びの声をいただきました![]()
|ご家庭でできる日常管理
犬 クッシング症候群は治療と同時に日常の観察も重要です。
1.毎日の飲水量を記録する
2.定期的に体重を測定する
3.食欲や元気の有無を観察する
4.皮膚や毛の変化をチェックする
5.半年〜1年ごとの健康診断を受ける
🐾まとめ
犬 クッシング症候群は「老化」と勘違いされやすい病気ですが、早期発見・早期治療で愛犬の生活の質を大きく改善できます。
静岡県浜松市近隣にお住いの飼い主様で、愛犬に「水をよく飲む」「お腹が出てきた」「毛が薄くなった」といった症状が見られる場合は、ぜひ当院にご相談ください。
TPC浜松動物総合病院は腫瘍治療を得意とし、犬 クッシング症候群の診断・治療に豊富な経験があります。大切なご家族である愛犬が、元気に長生きできるよう全力でサポートいたします。

 WEB予約
WEB予約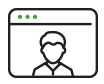 LINE相談
LINE相談